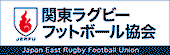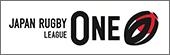名誉会長あいさつ Greeting
ラグビーは、試合後に仲間やファンと時間を過ごす選手が多い。子どもの頃から、仲間と素敵な時間を分かち合うことに慣れ親しんでいる。たとえ日本代表選手であっても、ファンとの距離が近い。支えてくれる人に会うことは当たり前だと思っている。
そうしたアフターマッチファンクションでは、ラグビーが、みんなに居場所のあるスポーツであることを実感できる。体が大きくても小さくても老いも若きも関係ない。多様で異なる仲間と助け合って勝つ。そのためには、自分の枠を超えていく。
高潔さ、謙虚さ、団結力、みなぎる意志、不屈の精神などラグビーで培われる資質は、人生に必要なものであり、生きていく力になる。ラグビーは、正面から勝負する時と身をかわす時を見極める知性のスポーツであり、しかも一人ではなく仲間がいてはじめて勝てる。自分が進んだ数メートルを犠牲に球を後ろにパスして、仲間を絶対的に信頼する心と、チームが一心同体となれる友愛が備わる。
濃密で豊かなラグビーの時間を分かち合った仲間は家族以上かも知れない。ラグビーは、仲間と集い、語らうことを教えてくれる「人生の学校」なのだ。
しかし、「人生の学校」は、耳には優しいが決してぬるいところではない。妨害を受けながら、遠いゴールラインをじりじり目指すフィールドは、ままならない人生の縮図でもある。障壁を突破して、目標に達するにはどうしたらいいか。仲間と楕円の球を追いながら、子どもの頃から、それを学ぶのだ。
北海道には、自然と人の生活のバランスのとれた社会風土があり、それがラグビーの精神性に適している。幸運なことに北海道の大地にラグビーは根付きやすい。その一方で、過疎化と気候条件の厳しさの下、大会運営、普及活動、施設整備に精励してきた北海道ラグビー100年の苦難の歴史がある。そのかいあって、若年層のラグビー人口はRWC2019以降も微増している。北海道ラグビーの未来は、プレーヤーたちにラグビーを継続してもらい、なおかつ新たなファンを獲得していくことにかかっている。
現在、北海道ラグビー協会が取り組んでいる事業「北海道ラグビーの日」は、全道の総力を結集してビッグゲームを開催することで、若い選手たちに忘れられない思い出と夢を持ってもらい、新たなファンを獲得して、未来世代にインパクトを与えるチャンスをつくる機会だ。試行錯誤の4年間の成果を見極め、必要とされる普及活動に資金を投入できる事業マネジメントと人材を求めながら、これからも歩んでいきたい。
Rugby players often spend time with friends and fans after a match. Since childhood rugby players have been used to sharing wonderful times with friends. Even as members of Japanese national team, they are close to their fans. Meeting the people who support them comes naturally to the players.
At the after-match function, you can feel that rugby is a sport where everyone belongs. It doesn’t matter whether you’re big or small, young or old, rugby is a game for everyone. We all win by helping each other as diverse friends. To achieve that, we should step out of comfort zone and rugby provides this opportunity.
Qualities nurtured through rugby, such as integrity, humility, solidarity, determination, and resilience, are essential in life and become a strength for living. Rugby is an intelligent sport that requires players to know when to confront head-on and when to evade, and victory can only be achieved by working together with friends. It embodies the willingness to sacrifice a few meters by passing the ball backward, absolute trust in friends, and a spirit of camaraderie that the team as one.
Friends with whom we have shared intense and fulfilling rugby moments may be more than just family. Rugby is a “school of life” that teaches us the value of gathering with friends and sharing meaningful conversations.
However, “the school of life” may sound appealing but it’s not that simple, The rugby field, where players inch toward a distant goal line while facing constant obstacles, reflects life itself, which is unpredictable and full of challenges. How can we overcome obstacles and achieve our goals? From childhood, we learn it by chasing the oval ball with friends..
Hokkaido has a social environment where nature and daily life co-exist in harmony, which suits the spirit of rugby well. Fortunately, rugby has taken root easily in Hokkaido. On the other hand, there is also a 100-year history of hardship in Hokkaido rugby-a story of dedication to hosting tournaments, promoting the sport, and improving facilities, all under the challenges of depopulation and harsh climate conditions. As a result, the number of young rugby players has continued to grow modestly since the 2019 Rugby World Cup. The future of rugby in Hokkaido will require keeping players engaged in the sport and a recruitment plan to attract new fans.
Currently, the Hokkaido Rugby Football Union is organizing the event “Hokkaido Rugby Day”, which brings together the entire region to experience a fun weekend of rugby. The goal is to create unforgettable memories and dreams for young players, to attract new fans, and provide an opportunity to make a lasting impact on future generations. Looking back on the results of the past four years, we have learnt good systems and have capable management and staffing to allocate funds to essential promotional activities. Looking forward to seeing you on Hokkaido Rugby Day.

一般財団法人
北海道ラグビーフットボール協会
名誉会長 田尻 稲雄
Honorary Chairman
Inao Tajiri
会長あいさつ
北海道ラグビー協会は、2019年に行われたラグビーワールドカップ日本開催を機にレガシー計画の一つであるタグラグビーの普及へ向けた大会の充実やスクール・ジュニアを含めた道内ボーイズ&ガールズへのラグビー体験会などの開催による普及育成、高校ラガーの全道大会での環境充実、並びに生涯にわたるラグビーライフの確立などラグビーをプレイする環境の充実を進めてまいりました。
日本代表などの国際試合や世界の名だたるプレイヤーが集まる国内最高峰のラグビーリーグであるリーグワンの試合の誘致や関東大学ラグビーの開催など、見る環境の充実も進めてまいりました。
各大会時にはグランド外での北海道の食を通した交流を深める楽しい場作りに向けた新しいこころみである「北海道ラグビーの日」の立ち上げなど、人と人のつながりによる感動の輪の拡大につながる、支える環境の充実にも挑戦してまいりました。
各取り組みの環境充実に向け、考え方の基本となるのが、ラグビーが独自に持つ誇らしい人間形成にも資する理念として定めたラグビー憲章「品位(INTEGRITY)・情熱(PASSION)・結束(SOLIDARITY)・規律(DISCIPLINE)・尊敬(RESPECT)」です。
この5つのコアバリューの深度化へ向け、基軸となるインテグリティーを中心とした研修会を各地域で開催し、充実した環境を提供できるよう指導者等へ向けた人材育成にも取り組んでおります。
ラグビーは1823年イングランド、ラグビー校でのフットボール(今のサッカーとは異なる学校ごとの独自なルールであった)の試合中にウエッブエリス少年がボールを持って走り出したのが起源として伝えられており、今日まで200年を超える歴史が刻まれてきました。
北海道でも1924年(大正13年)には北海道大学に小さなサークルを結成して楕円のボールを持って走りパスをした活動の記録が残っており、それが北海道ラグビーの起源となっております。
北海道のラグビーの歴史が100年を超えることができたのも、今日まで支えてくださった多くの先輩、そしてかかわっていただいた、お一人おひとりの存在そのものが北海道のラグビーの歴史です。かかわって頂いた全ての皆様に心より感謝を申し上げます。
ラグビー憲章に定めるコアバリューを誠実に実行できるようラグビー環境の充実に向け取り組みを続けて参ります。引き続き皆様のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

一般財団法人
北海道ラグビーフットボール協会
会長 津軽 敦志
理事長あいさつ
大自然に恵まれた北海道で、人を自然に返してくれるような魅力あるラグビーと出会い、高校生の指導者となり、これまで歩んできました。その中でラグビー協会にも携わり、今は理事長を任されて、ラグビーの魅力を発散する仕事に務めております。
指導者から見たラグビーの魅力は、多様性、精神的な成長、そして「ノーサイド」の精神にあると思っています。ラグビーは、体格やプレースタイルが異なる様々な選手が、それぞれの個性を活かしてチームのために貢献できるスポーツです。また、責任感や協調性を養い、人間的な成長を促す側面も魅力です。さらに、試合終了後にお互いを尊重し合う「ノーサイド」の精神は、ラグビー特有の価値観として、指導者にとっても大きな魅力となっています。
ラグビーは、15人という大人数でプレーするため、様々な個性を持つ選手が活躍できる場があります。体格、スキル、性格など、異なる特徴を持つ選手たちが、それぞれの持ち味を生かしてチームに貢献できる点が多様性の魅力です。
またラグビーは、単に技術を競うだけでなく、チームのために行動すること、仲間と協力すること、そして困難に立ち向かう精神を養うことができます。また、責任感や規律を学ぶことで精神的に成長できる。それも指導者として重要視する点です。
そして試合終了後、敵味方なく互いを称え合う「ノーサイド」の精神は、ラグビーの大きな特徴であり、指導者も選手も大切にすべき価値観です。
もちろんスポーツなので勝つことを目指します。ラグビーは、ボールを後ろにしかパスできないという制約の中で、様々な戦術を駆使して相手を攻略していく奥深さがあります。指導者は、選手に状況判断力や決断力を教え、チームとしての戦略を練る楽しさを伝えることができます。
しかし最も大きな特徴は、ラグビーを通じて、協調性、リーダーシップ、問題解決能力など、社会に出ても役立つスキルを身につけることができることです。フェアプレーを重んじるスポーツであり、指導者は、ルールを守ること、相手を尊重することの大切さを教え、スポーツマンシップを育むことができます。
これらの要素が、指導者にとってのラグビーの魅力を構成していますが、世の中には、それでも多くの人々が様々な考えを持って暮らしていて、ラグビーの価値観にはそぐわないハラスメントが生じることもあります。そうしたトラブルに対処することも、指導者の仕事であり、理事長の務めでもあります。
北海道の豊かな自然は、恵みだけでなく厳しい現実も突き付けてくれます。それに向き合い、耐え忍んで生き抜くことも、ラグビーを通じて後世に伝えていくことだと感じています。
これからも「北海道ラグビーの日」で、北海道のラグビー仲間が一丸となって盛り上がり、さらにラグビーの価値を高めて、広くいつまでもラグビーの魅力を発散できるよう務めて参りたいと思います。

一般財団法人
北海道ラグビーフットボール協会
理事長 佐藤 幹夫